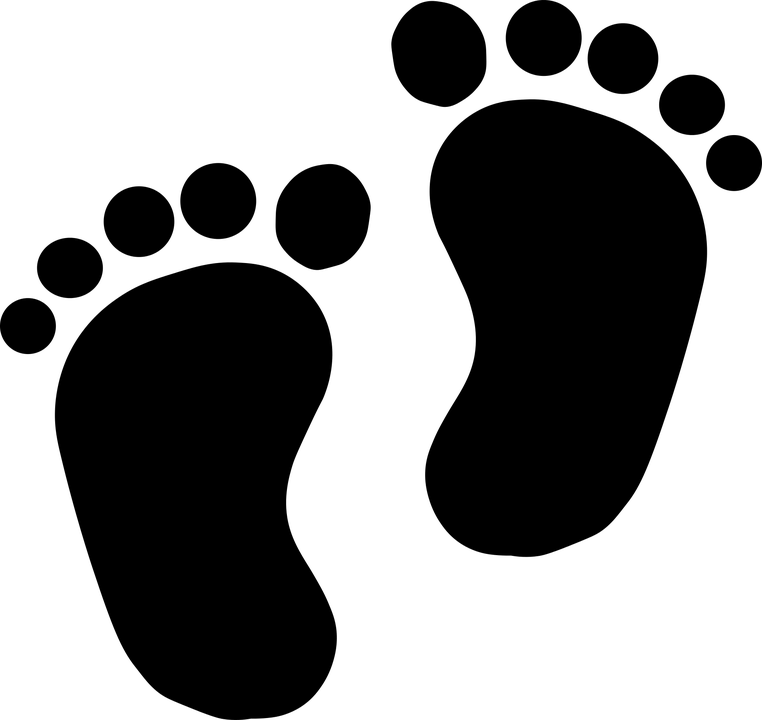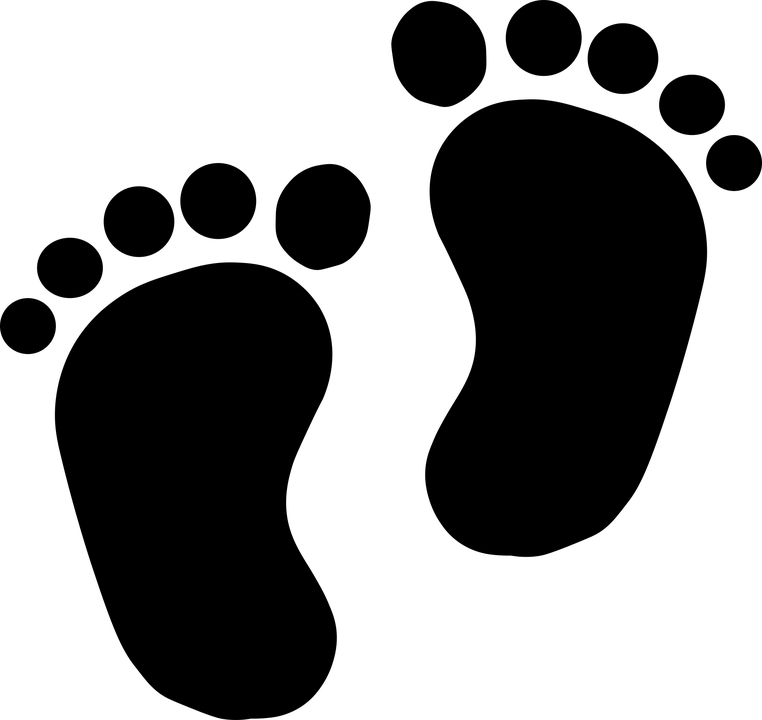靴をぬいだとき、指やそのつけ根のあたりに、赤くはれたり、固くなったりしているところはありませんか?
もしあれば、それがタコや魚の目の予備軍です。
たいしたことないと放っておくと、ひどくなると痛くて歩けなくなることもあり、日常生活に支障をきたしてしまいます。
かたくなった皮膚の中心に芯があり、押したりつまんだりすると痛みを伴い、再発しやすいので予防が大切です。
では、対策はないのでしょうか?
原因から予防法を見ていきましょう!
原因
原因のほとんどは「足に合わない靴」です。たとえば小さめの靴をはいていると、足の指やつけ根などが靴にあたり、圧迫され続けます。
靴幅がせまく、指が両側から圧迫されると、指と指の摩擦が起こり、こうした圧迫や摩擦の結果 、皮膚は自分を守るために固くなり、タコや魚の目になります。
大きめの靴は、足が靴の前側へとすべっていき、やはり指やつけ根のあたりが圧迫されて、同じことが起こるのです。
その合わない靴で、長時間の立ち仕事や運動などをしてしまうと、連続的に刺激をあたえることになり、できてしまうのです。
症状
魚の目は、常に圧迫や摩擦を受けている部分にできます。
皮膚の角質層が厚くなり、中心部分に芯があるのが特徴で、同じように角質が厚くなるタコには芯はありません。
魚の目の場合は、中心にできた硬い芯が徐々に皮膚の深くまで入り込み神経を刺激して痛むようになり、重症化すると魚の目を除去するのにも時間がかかってしまいます。
足の指の付け根、親指や小指の外側、足指の関節がまがっているハンマートゥの場合は足指の上側など、圧迫されやすいところです。
予防
魚の目ができる原因は圧迫や摩擦です。
自分の足の指や指の付け根など皮膚が固くなっているところがあると、そこは何らかの圧迫や摩擦が生じている可能性が高く、放っておくと角質が厚くなってきて魚の目になってしまうかもしれません。
早めに角質除去などのフットケアをすることで予防できます。
また、靴のサイズがあっていないことも魚の目ができる原因の一つで、底の薄い靴も地面からの圧力が強くなるので、クッション性のあるインソールを使うことで魚の目やタコの予防になります。
治療
初期の段階で角質が固くなっていても痛みがあまりない場合ならば、市販されている魚の目・タコ用の保護パッドやクッション性のあるインソールを使うことで改善することがあります。
また、芯ができてしまった魚の目でも市販のサリチル酸配合のスピール膏などを貼り、厚くなっている角質を柔らかくし少しずつ削っていくことで魚の目を除去することができますが、魚の目は芯を完全に除去しなければ再発することがあります。
セルフケアで除去し切れない魚の目や痛みがあるような魚の目を除去するためには皮膚科専門医を受診し適切な処置をしてもらいましょう。
まとめ
最後に根本的な原因である、足にあっていない靴やアンバランスな姿勢や歩き方などを改善しないと再発してしまいますので注意が必要です。
ヒールのある靴で足を酷使すると、ある特定の部分だけ足裏が固くなることってありますよね?
そんな固くなった角質を放置すると
マメ、タコ、ウオノメの原因に・・・
そうなってしまう前に、固くなりやすい人などにはこちらがおすすめです。
夜寝る前に塗ると、歩くのも辛かった足裏をピンポイント集中ケアできます。
また、糖尿病などの持病がある場合には、自分で魚の目を除去しようとして細菌に感染する恐れもありますので、自己判断をしないで、必ず皮膚科の専門医に診てもらうことにしましょう。